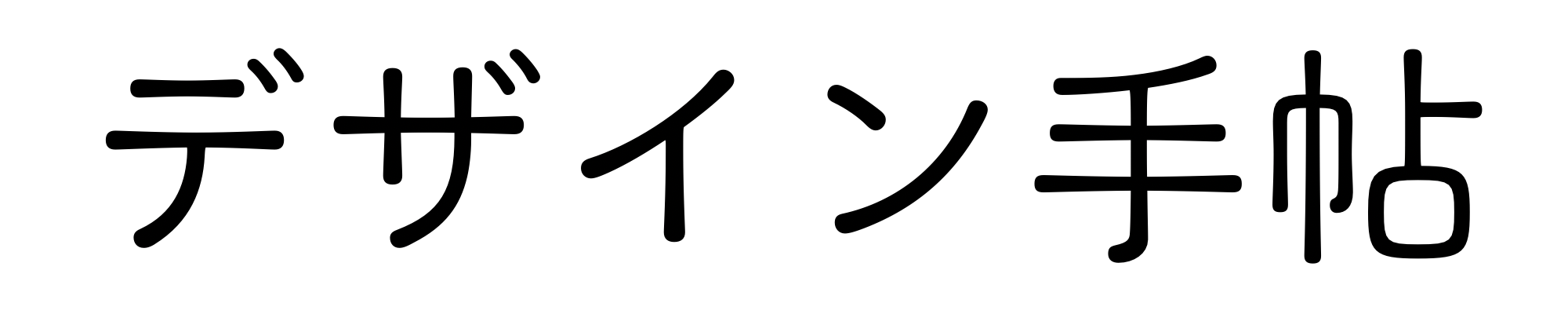【色がくすむ?】生成AI画像を印刷するときに気をつけたい「色」のポイントまとめ

最近はMidjourneyやDALL·E、chatGPTなどの生成AIを使って、美しいビジュアルを手軽に作れるようになってきましたよね。でも、その画像を印刷しようとすると…「えっ、色が全然違う!?」「くすんでる…」なんて驚いたことはありませんか?
実は、生成AI画像を印刷する際には“色の落とし穴”がたくさんあるんです。
この記事では、生成AI画像を紙に印刷するときに色の面で気をつけるべきポイントを、わかりやすく解説していきます。
RGBからCMYKに変換が必要
生成AIで作られた画像は、基本的にRGBカラー(Red・Green・Blue)で構成されています。
これは画面上で表示するための色で、発色がとても鮮やかなのが特徴です。
一方、印刷はCMYKカラー(Cyan・Magenta・Yellow・Black)というインクの組み合わせで表現されるため、RGBより色の表現範囲が狭く、鮮やかな色がくすんで見えることがあります。
印刷に使う前に必ずCMYKに変換しよう
- Illustratorなら:[ファイル] → [ドキュメントのカラーモード] → [CMYKカラー]
- Photoshopなら:[イメージ] → [モード] → [CMYKカラー]
変換後、色のくすみや見た目の変化をチェックして、必要に応じて調整しましょう。
鮮やかすぎる色はくすむ可能性大
AI画像は、RGBの性質上、蛍光色のような明るいピンク・ブルー・グリーンなどがきれいに出ます。
でも、それをCMYKで印刷しようとすると…
- 蛍光ピンク → くすんだサーモンピンク
- 鮮やかな青 → 落ち着いた水色
- ネオン系カラー → 表現できずに色が破綻
といった具合に、どうしても発色が鈍くなるのです。
彩度が高すぎると不自然に見えることも
生成AI画像は、初期状態で彩度やコントラストが強めになっていることが多いです。
印刷すると、その強さが悪目立ちしてしまうことも…。
対策
- CMYK変換後、彩度を少し落とす
- コントラストを微調整してトーンを整える
これだけで、印刷での仕上がりが自然になります。
印刷に必要な解像度(300dpi)を確保できているか?
色の問題とは少し離れますが、解像度の低い画像を印刷すると色もぼやけて見えます。
印刷には「300dpi」が基本。
たとえばA4サイズに印刷したいなら、最低でも2480×3508ピクセルくらいの大きさが必要です。
生成AIの出力画像が小さい場合は、生成時の設定やリサイズに注意しましょう。
用紙によって色の出方も変わる
同じ画像でも、印刷する紙によって発色の印象が大きく変わります。
| 用紙の種類 | 特徴 |
|---|---|
| コート紙(光沢紙) | 発色が良く、AI画像に向いている |
| マット紙(つや消し) | 色が落ち着いて見える、ややくすむ |
| 上質紙(コピー用紙のような紙) | 発色が鈍く、鮮やかな色が出にくい |
「なるべく画面に近い色味で見せたい」なら、コート紙や光沢紙を選ぶのが無難です。
多少色がくすんでしまうのは仕方ない?
はい、これは印刷という仕組み上、ある程度は避けられない現象です。
RGBカラーは光で表現されているため、画面上ではとても鮮やかに見えます。
一方、CMYKカラーはインクの重ね合わせによって色を表現するため、再現できる色の範囲がRGBよりも狭く、特にビビッドな色やネオン系の色はくすんで見えることがあります。
これはプロのデザイナーや印刷会社でも共通認識されている「印刷あるある」で、完全に画面どおりの発色にすることは不可能と言われています。
そのため、「印刷では多少くすむもの」という前提で、色味を事前に調整したり、紙や印刷方式を選ぶ工夫が大切になります。
まとめ:生成AI画像を印刷するなら、色変化に注意!
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 色空間 | RGB→CMYKへの変換を忘れずに |
| 発色 | 鮮やかな色はくすむ前提で考える |
| 彩度 | 印刷に合わせてトーン調整を |
| 解像度 | 300dpi以上あるか要確認 |
| 用紙 | 発色重視なら光沢系の紙を選ぶ |
生成AIの画像はとても魅力的ですが、印刷の仕上がりを意識して調整することが大切です。
少しの工夫で「画面と全然違う…!」というギャップを減らせますので、ぜひ今回のポイントをチェックしてみてくださいね。